「なんでおるん?」
7月7日の3年間。
七夕の日だけ元彼女に会ってたことがある。
初めて付き合った彼女でもなければ、長く付き合った彼女でもない。
半年だけ付き合ってた彼女。
今まで死んでないから生きている、なんて青臭いことを大真面目に思い込んで生きてきたのだけれど、人生には、ほとんどのことがただの暇つぶしで、全てを捨ててもいいと思える瞬間がある。
思い出だけでは生きていけない、思い出がないと生きていけない。
こびりついた記憶の話し。
#記憶の断片小説
7月7日七夕の3年間 元彼女に会っていた話
「なんでおるん?」
「おまえこそ」
20代の頃、半年だけ付き合ってた元彼女。
「元気だった?」
「そっちは?」
「…………」
「そっか……」
待ち合わせはいつも夜の公園だった。
どこにでもある小さな滑り台とブランコだけの小さな公園。
街灯から少し離れたいつもの場所で煙草をくわえていると、声をかけてくるのはいつも彼女だった。
「火、くれる?」
タバコを咥えた彼女の顔が近づく。
タバコを咥えて顔を近づける。
「1年で1番好きな日は?」
「七夕」
「ふーん、なんで?」
「1年で1回しか会えないのにずっと両想いなんだよ」
もう30も近いのに青臭いことを言ってる。
「ふーーーん。1年で1回しか会えないからずっと両想いなんじゃない?」
「かもしれんな」
なんてことはない。
いつものたわいない会話をして、あてもなくドライブするか彼女の家に行くのが日常だった。
「私が生まれたのは冬だけどね」
「知ってる」
半年ほど、飽きもせずに同じことを繰り返したのは、最初から期限付きの付き合いだったことを知ってたからかもしれない。

「今日が最後みたい」
「…………」
体の芯が凍り付く。
胸の奥の辺りにズシンと重さを感じて、バレないように足元に力を入れる。
周りが見えなくなるような年じゃない。
一時の熱に浮かされてすべてを捨てる、なんて決断はできなかった。
「…………」
「そっか」
傷つけあったわけでもなければ情熱的だったわけでもない。
声を張り上げてケンカすることもなければ、街中で見つめ合うようなデートをすることもなかった。
他人から見れば付き合ってることさえわからなかったかもしれない。
「会わなければよかったね」
「…………」
「…………」
「俺は……お前に会えてよかったよ」
自分を疎かにするところが嫌いだった。
他人の心配ばかりするところが嫌いだった。
いつも自分を後回しにするところが嫌いだった。
分かったフリして我慢してるところが嫌いだった。
嫌いなところが好きだった。
「もっと早く会いたかった」
「でも会えた」
「…………」
「ちゃんと幸せになれよ」
「…………」
彼女は俯いて静かに震えてる。
指先からタバコが滑り落ちる感覚に気づいて歯を食いしばる。
背中を向けて揺れる街灯を見上げた。
その日、彼女は元彼女になった。
7月7日の七夕。
小さな滑り台とブランコしかない夜の公園。
「なんでおるん?」
「おまえこそ」
声をかけられて咥えた煙草を落とした。
「元気だった?」
「そっちは?」
もう2度と会うことはないと思ってた元彼女。
「…………」
「そっか……」
別に期待していたわけじゃない。
と、今まで思っていたけど、きっと期待していたのかもしれない。
「やっぱり雨だね」
「そーだな」
「七夕っていつも天気悪いらしいよ」
「知ってる」
なんてことはない。たわいない会話をしてるだけでよかったんだけどな。
それから3年間。
七夕の日にだけ元彼女に会ってた。
「また会ったね」
「そーだな」
「今年も雨だね」
「そーだな」
「来年は晴れるかな」
「たぶん……晴れる」
「ここはそーだなでしょ」
「……そーだな」
「来年は晴れるんだ?」
「そろそろな」
「そっか」
「…………」
「火、くれる?」
「やめたんじゃねーのかよ」
「これが最後」
タバコを咥えた元彼女の顔が近づく。
タバコを咥えて顔を近づける。
「もし…………」
「…………」
元彼女は何かを言いかけてやめた。
俺もそれを聞こえないふりをした。
次の七夕は晴れだった。
小さな公園で指先に熱を感じる。
最後のタバコが灰になって初めて、自分の犯した間違いの大きさに気づいた。
あの日からは、約束もしていない1年に1度やってくる日を楽しみに生きていたのかもしれない。
なんとも滑稽でつまらない話だ。
すべて終わってから気が付いた。
きっとあの時、声をかけなければいけなかったんだと思う。
結局、俺は大事な時に何も出来なかった。
分かったフリしてたのは俺だった。
胸の奥がズッシリと重い。
最後の彼女でもなければ、情熱的な恋愛だったわけでもない。
ただ真剣に、好きだった元彼女。
しあわせになってんだよな?
執筆よる
#記憶の断片小説
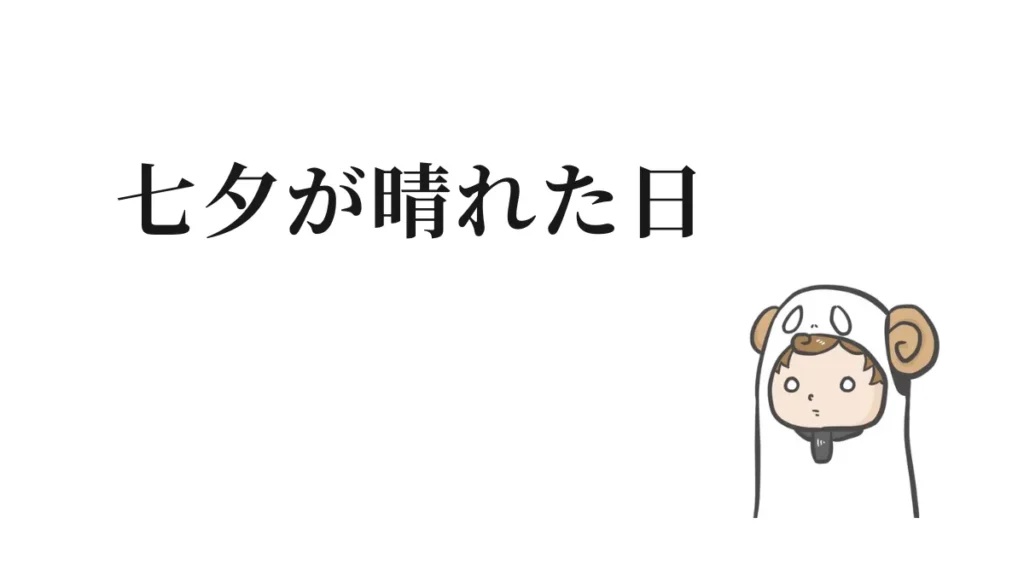


コメント